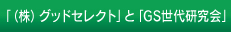短歌で詠むニッポン 発刊のお知らせ 西村晃 著 文芸社 1000円+税
2025年4月18日
14年目の誕生日
2025年4月 3日
戦後80年の節目
2024年12月25日
2025年のキーワード 昭和100年、内外前後左右上下、八方注意怠れず
2024年10月23日
住宅事情激変の予兆
・2025年4月 (2)
・2024年12月 (1)
・2024年10月 (1)
・2024年8月 (4)
・2024年5月 (1)
・2024年4月 (1)
・2023年12月 (2)
・2023年6月 (2)
・2023年3月 (1)
・2023年1月 (1)
・2022年11月 (1)
・2022年10月 (2)
・2022年9月 (1)
・2022年8月 (2)
・2022年7月 (1)
・2022年5月 (1)
・2022年4月 (2)
・2022年2月 (2)
・2021年12月 (3)
・2021年11月 (3)
・2021年10月 (3)
・2021年9月 (9)
・2021年8月 (2)
・2021年7月 (7)
・2021年6月 (14)
・2020年11月 (1)
・2020年9月 (1)
・2020年3月 (1)
・2020年2月 (1)
・2019年11月 (1)
・2019年10月 (2)
・2019年7月 (2)
・2019年5月 (1)
・2019年2月 (1)
・2018年10月 (2)
・2018年9月 (2)
・2018年6月 (1)
・2018年5月 (3)
・2018年4月 (3)
・2018年3月 (1)
・2018年2月 (2)
・2018年1月 (1)
・2017年11月 (3)
・2017年10月 (11)
・2015年9月 (1)
短歌で詠むニッポン 発刊のお知らせ 西村晃 著 文芸社 1000円+税
2025年6月22日
~短歌はマーケティングに通じる~
いつもお世話になっております。
さてこの度、初めての短歌の本を出版しました。
心筋梗塞の手術を経て群馬に移住したことをきっかけに短歌と俳句を始めました。
みずみずしい自然、豊かな食材などこの地のすばらしさが私の好奇心を呼び起こしたことは間違いありません。コロナの雌伏の日々、そしてようやく移動や会合が自由になった喜び、国の内外を気ままに訪ねることのありがたさも歌に詠みました。周りを見回すと定年前後の同輩たち、職場環境の激変に戸惑う人たち、そして急速なIT化など多くの気づきもありました。
作歌のプロセスは観察力によるインプットをどうアウトプットに結び付けるかです。それはビジネスと全く同じではありませんか。
是非学びのヒントとしてお読みください。
なおこの本は7月1日より全国の書店、ネットでも販売されます。
お知り合いにご紹介いただければありがたく思います。
SNS拡散、大歓迎です。
14年目の誕生日
2025年4月18日
今日は誕生日である、と言っても私ではない。
2011年4月18日、「GS世代研究会」が発足した。
「GS世代」とは私が本で紹介した造語で、ゴールデンシクスティーズ、「黄金の60代」という意味だ。もちろんそこには「グループサウンズが好きな世代」という意味も掛けている。
2011年と言えば、戦後のベビーブーム世代が60代になり退職年齢に達する頃だった。退職金も入り住宅ローンも完済、子育ても峠を越えてようやく豊かな時間と、少しばかりの余裕資金を持つ頃で、これからしばらくは彼らがどんな消費行動をとるかが重要なマーケティングのポイントと、「GS世代攻略術」という本に書いた。すると多くの賛同者が集まり「GS世代研究会」という勉強会を作ろうということになった。
最初の発起人会が開かれたのが2011年4月18日、六本木のハリウッド化粧品の会議室に22の企業と自治体が集まった。マスコミにも取り上げられ会はみるみる成長してゆく。特徴は多くの自治体と、大企業と地方の中小企業が一堂に会したこと、意外にこういう会はないものだ。最盛期自治体と企業数は400を超えた。
「GS世代研究会」はシンポジウムや分科会、見学会なども開催しつつ、ショッピングセンターなどでの販売会、カタログ販売、クルーズなど様々な活動を展開、特に「歩き愛です(あるきまです)」と名付けたウォーキングイベントは自治体が開催し、「GS世代研究会」の企業がたくさんの参加賞を用意して全国150か所以上で開催する盛り上がりを見せた。
残念ながらコロナ禍でそうした活動は途切れてしまったが、いまも事業会社「グッドセレクト」を窓口に細々ながらマッチング活動を行い、高齢者マーケティングのお手伝いをしている。
14年前の「GS世代」は今年ほぼ全員が後期高齢者となり、日本経済は明らかに縮小傾向をたどってゆく。アメリカの保護貿易主義への傾斜もあり、日本は内外ともにブレークスルーが求められている。
戦後80年の節目
2025年4月 3日
戦争を知らないベビーブーマーがほぼ全員75歳以上の後期高齢者となる今年は、日本にとって大きな試練の年になった。
米ソ対立の代理戦争でもあった朝鮮動乱で日本はアメリカ主導の自由陣営の太平洋の防波堤としての役割も担うことになった。
自衛隊の発足、日米安保条約の締結は日本が望んだというよりは当時のアメリカの強い意志によるものだった。
アメリカの傘のもと、日本は経済復興に邁進しやがてアメリカをしのぐような工業力を持つにいたる。国内需要が限られる日本にとって広大なアメリカ市場に進出することは大きな魅力だった。
アメリカから見れば、日本は安全保障をアメリカに委ね、注力した経済力でアメリカの産業を苦しめてきた、という見方もできたのかもしれない。
日本はアメリカを守ってくれるわけでもない、一方的にアメリカが日本を守るのはおかしい。日本車がアメリカ市場を席巻しているのに、日本はアメリカ車を買わない。
基幹産業の鉄鋼企業を日本は買収するのか。
いくらでも反論はできるが、アメリカの思い込みは相当なものだ。ある意味、トランプ大統領の登場は必然だったのかもしれない。
戦後80年、これまで日本が平和にひたすら経済発展に邁進できた「アメリカという恩恵」が消えてなくなるかもしれない、という大きな節目を迎えた。日本同様アメリカとの同盟関係の恩恵に浴してきたヨーロッパも、あるいはカナダもメキシコも同様にこれからはアメリカに頼らずやっていかなければならないと覚悟を決めつつある。
思えばトランプは「自分勝手な野郎」である。しかし、世界の大国で現在も過去も見回してみて大国はいつも基本的に「自分勝手な野郎」ばかりだった。歴史はそれは今に始まったことではないと教えてくれている。
時間はかかるだろう。80年もむさぼった太平のツケを払うのだから、それは大変だ。
しかしほかに生きる道は、ない。
周辺国と同盟を模索し安全保障の新たな枠組みを構築する。アメリカ一辺倒に頼る経済ではなく、世界をひろく見渡して日本製品の販路を開拓してゆく努力をするしかない。
戦後80年、これまでとは違う世界が訪れようとしている。
圧倒的な優位性を誇ったアメリカはもういない。
覚悟を決める時がやってきた。
2025年のキーワード 昭和100年、内外前後左右上下、八方注意怠れず
2024年12月25日
2025年、令和7年は昭和100年にあたる。コロナの苦難からはようやく脱しつつあるが世界と日本は問題が山積、あちこち目を光らせていないとたちまち八方塞がりとなりかねない。戦後80年、秩序が崩れ最大の試練の時を迎えようとしている。
「内」 総選挙の結果自公政権は過半数を取れず、新たな政党を政権に囲い込むこともできなかった。政策ごとに野党の協力を求める綱渡り状況が続く。
野党にしてみれば、政府の政策に反対ならばいつでも内閣不信任案を提出、可決の可能性は大きくなっている。党内にも反石破勢力がいるから欠席戦術に出れば、たちまち不信任案は
可決する。解散総選挙はもはやできないから内閣は総辞職に追い込まれかねない危ない橋を渡らねばならない。戦後政治の一大転機の年となりそうだ。
しばらくは「内閣不信任案」が政治の大きなテーマとなる。
「外」 外交である。アメリカ大統領選挙でトランプ大統領が誕生した。アメリカ第一主義で内向きの保護貿易、安全保障政策の後退で世界と日本は大きな影響を受けそうだ。外交が暮らしに
直結するかつてなく重要な局面を迎えた。中国はじめ貿易相手国へ大幅関税をかける、第二のプラザ合意のようなドル安政策をとる、台湾、韓国、日本などの防衛費負担をさらに求め
る、といった施策を次々に繰り出してくる可能性がある。どれも重要な問題で今後の日本の未来を左右しかねない。来年は新大統領の動きから目が離せない。
「前」 戦後80年という長い時間が過ぎたが、いまは新たな「戦前」かもしれないという不安が地球を覆っている。特にロシア、中国、北朝鮮にイランを加えた枢軸4か国の動きに目が離せ
い。北朝鮮がロシアに派兵してウクライナ戦争に加担したこと、さらに北朝鮮は武器をイランにも供給、そのイランとイスラエルが対峙していることなど今後の戦火拡大を予想させ
る。また中国が台湾へ、北朝鮮が韓国へ戦いを仕掛ければ、西側諸国と全面戦争になりかねない。第三次世界大戦はけっして空想の世界の話ではなくなった。
「もはや戦後ではない」から「今や戦前」ともいうべき国際情勢だ。
「後」 ひるがえって日本国内を見ると2025年は大きな節目である。戦後のベビーブーム世代のほぼ全員が「後期高齢者」に仲間入りするからだ。
後期高齢者になるとそれまでと比べて健康を維持することが難しくなり行動範囲が狭くなることは間違いない。後期高齢者の10人に1人は高齢者施設などの既に入所あるいは入所待ちの状態でもある。
前期高齢者のころは定年後、退職金も入り、子育ても終わり、住宅ローンも完済して旅行や趣味などに費やす金銭的、精神的そして体力的ゆとりもあった人たちも、次第に家に籠りがちになってくる。つま
り消費人口の減少をもたらすことを意味する。日本経済はいよいよ目に見えて縮小してゆく。
「左」 左翼とひところ言われた社会主義陣営の中国とロシアは、国家が管理しながら資本主義を取り入れ、かつて彼らが敵対していた帝国主義的な国家戦略を今度は自分たちが推し進めている。
中国は南シナ海の海域に進出、べトナムやフィリピンと領有権争いが過熱化しているし、アフリカや中南米でも経済援助を背景に支配権を広げている。ロシアもアフリカなどに親露政権を樹立する
べく工作活動と援助活動を進めている。国連で対露経済制裁などが進まないのも西側世論とは裏腹に親露諸国が多いことによる。発展途上国が親中国、親ロシアに色分けされて行く中で日本
がどう資源と経済市場を確保してゆくか課題となっている。
「右」 インフレの進行で生活苦にあえぐ国が増えて、自国第一主義を訴える右翼勢力の台頭が著しい。トランプ政権樹立もその流れの中にある。ヨーロッパでも各国軒並み右翼勢力が台頭しネオナチズ
ムが政治の前面に躍り出ている。日本でも既成政治に飽き足らない人や生活苦に喘ぐ人が多くなれば極右勢力の台頭を招いたり治安の悪化に見舞われる心配も現実のものとなる。
「上」 これには二つある。
一つは日銀の金利引き上げが本年どこまで進むか、大きなポイントだ。 昨年夏の金利引き上げが思わぬ株価暴落を引き起こしたことから日銀は金融引き締めのスピードに神経を使う。
アメリカが金利を引き下げれば日米金利差は縮小、為替は円高に向かうことが予想される。ドル円相場を睨みながら年に2回程度の引き上げを行うものとみられる。
もう一つ賃上げも重要なテーマだ。
昨年は、大企業はもちろん中小企業でも予想を上回る賃上げが行われたものの、その後の物価上昇で実質賃金は再びマイナスに転じた。25年春闘で継続的な賃上げができないと真のデフレ脱
却にはならないというが、企業業績に陰りが出ていることや中小企業に賃上げ余力があるかという問題もあり、どの程度の規模の賃上げが実現できるかが今後の消費拡大にも関わる大きなテーマ
となる。
「下」 前項とも関係するが、3年目に入った物価上昇が下げに転じるか、これも今年の注目だ。少数与党は野党からの生活費補填の要求にどうこたえてゆくか。財政肥大化とのにらみ合いだ。ま
た国際情勢次第で原油価格、食糧価格急騰の心配もある。緩やかなインフレが望ましいという政府日銀だが、国民生活の窮乏も無視できない。物価が下がるか、注目したい。
「内」「外」「前」「後」「左」「右」に「上」「下」と八方に目配りが欠かせない2025年、昭和100年である。
住宅事情激変の予兆
2024年10月23日
2025年、日本は大きな節目を迎える。
戦後のベビーブーム世代、団塊の世代がほぼ全員後期高齢者の仲間入りをするからだ。後期高齢者になるとそれまでと比べて健康を維持することが難しくなり行動範囲が狭くなることは間違いない。後期高齢者の10人に1人は高齢者施設などに既に入所あるいは入所待ちの状態でもある。前期高齢者のころは定年後、退職金も入り、子育ても終わり、住宅ローンも完済して旅行や趣味などに費やす金銭的、精神的そして体力的ゆとりもあった人たちも、次第に家に籠りがちになってくる。つまり消費人口の減少をもたらすことを意味する。
私はこの世代がまだ40代のころから30年以上にわたり継続観察してきた。
60年代から70年代にかけて高度成長で人手不足という時代背景もあり、東京など大都市へ地方から一斉に若年労働力の移動がおきたがその中心がこの団塊の世代だった。全共闘ブーム、結婚ブーム、第二次ベビーブームと常に社会現象の中心にあった彼らは、東京都内の下宿や賃貸アパートから郊外の団地、そしてマイホームへと住宅のニーズを移してゆく。
当時の評論家大宅壮一は団塊世代の住宅事情を「方荘棟字」という四字熟語風に表現した。
すなわち、学生時代は下宿で「...様方」の三畳一間、就職すると「あけぼの荘」「富士見荘」と言った木賃アパート、結婚して子供ができると2DKの団地に入ろうと高い競争率に挑戦する。そしてようやく手にしたマイホームは超郊外の農地の中で住所は「字」だった、というわけだ。
首都圏においてその「字」を供給したエリアは国道16号沿線であった。山手線のターミナル駅まで電車で小一時間、京浜急行や東海道線で言えば横浜周辺、小田急線なら町田や相模大野、京王線や中央線なら八王子、西武線や東武線なら川越、京浜東北線なら大宮、常磐線なら柏、総武線なら千葉という具合に首都圏30キロから40キロ圏を環状する国道16号とぶつかるあたりの駅周辺にニュータウンが形成された。
現在ならもっと都心から遠いところまでマンションがならび、駅近くに若いサラリーマンが戸建て住宅を一次取得するのは至難の業であるが、団塊の世代がバブル期以前に買い求めたこのエリアのマイホームはおおむね土地付き一戸建てだった。80年代一世を風靡したテレビドラマ「金曜日の妻たちへ」の舞台は、まさに田園都市沿線のこのエリアが舞台で、ニューファミリーは田舎に暮らす親の世代とは別居し、これまでの日本の家庭とは異なる新しい価値観で生活を楽しんだ。
それから40年近くが過ぎた。
かつてはニューファミリー消費のメッカとして多くの商業施設が立ち並んだ国道16号エリアは、いま全国でも有数の後期高齢者の急増エリアとなった。地方出身の団塊の世代が後期高齢者、そこで生まれた団塊ジュニアも中高年だ。首都圏に住む団塊の世代は現在でも約155万人、中でも国道16号が通る神奈川、千葉、埼玉3県が目立つ。団塊の世代の持ち家が土地付き戸建てである場合が多かったので、そこに二世帯住宅を建て直したという例も多いが、団塊ジュニアが別居して独居老人世帯も目立つ。あと10年もすれば、このエリアで家の相続問題が発生することになる。
団塊ジュニアは親の世代ほど子供の数が多くはなく、しかも首都圏どうしあるいは近畿圏どうしの結婚例が多い。団塊の世代の時は東北や九州から首都圏に出てきた人が結婚するようにお互いの郷里が遠距離という場合も多かったものだ。
その点団塊ジュニアは結婚した相手も首都圏に持ち家があるケースもあるから、何人もの子供が一軒の親の家の相続権を争うということは少ないとみられる。
例えば団塊ジュニアの長男が親の家を相続したとして、団塊ジュニアがそこに住み続けるのかは疑問だ。団塊ジュニアもそろそろ定年後のことを考える。リモートワークの時代でもあり、親から引き継いだ土地付き一戸建てを売却したカネで、もっと都心のタワマンに移ることもあるだろうし、逆にもっと東京から離れた超郊外に移住すれば、家の売却金を相当残して老後資金を確保したうえもっと広い家に住み替えることも可能なわけだ。
いずれにしてもこれから十年、首都圏の住宅事情は40年に一度の大激変を迎えることになる。
スマホが滅ぼしたもの
2024年8月26日
「アート引っ越しセンター」の社名は「アート」だと電話帳のトップに名前が掲載されるという計算から生まれた。昔は引っ越しを考えるとまず電話帳で業者をさがすものだったのだ。
電話帳は生活に欠かせないツールだった。その電話帳がいよいよ消えるという。
電話帳だけではない。「分厚いもの」は軒並み時代遅れになりつつある。
広辞苑などの大型の辞書、百科事典、イミダス・知恵蔵・現代用語の基礎知識・・・。
会社四季報に時刻表までもがどんどん消えつつある。
日本で本格的な時刻表が初めて発売されたのは、明治27年(1894年)の10月5日のことである。「汽車、汽船旅行案内」という名前がついていた。小説や紀行文など読み物のページもあり、旅行ガイドブックを兼ねたものだった。
私は中学生のころから時刻表を愛読していた。当時はお金がないから時刻表の中で架空の旅を楽しんでいた。やがて国鉄全線踏破を目指すようになると,周遊券とそれで乗れる夜行の急行で全国を回った。夜、下りの列車に乗ると反対の上りのページの時刻表を開き、何時何分にどのあたりですれ違うかを予想して一晩中起きていたものだった。
時代は下り、新幹線中心のダイヤではあまりにも単純で時刻表をめくる楽しみも失せた。昔の時刻表は欄外に該当する路線で販売している駅弁の紹介などもあったが、いまは地方の駅で駅弁を販売しているところも少ないし、車内販売さえなくなりつつある。少し大きめの駅でも入っているのはコンビニ、これでは地方色も薄れる一方だ。
時刻表がなくてもスマホで検索できる時代、これではもはや趣味とは言えなくなってしまった。
また買ってしまった・・
2024年8月21日
前橋にはさまざまな小売業が進出しているため、欲しいものが最安値で買えることに満足している。生鮮三品はじめ家電、家庭用品、家具などあらゆるものがそれぞれの大型量販店で手に入るが、もう一つ私が満足しているのがシャトレーゼ、市内に三店舗ある。
山梨から全国に展開する菓子のチェーンだ。山梨の農産物とアルプスの天然水をベースに地方都市発ならではの低価格商品で人気を集める。オリジナリティあふれる和洋菓子を豊富に用意しているが、中でも人気があるのがアイスクリームや氷菓子で、夏場は商品が払底するほどの売れ行きである。
シャトレーゼは私が主催する「GS世代研究会」のメンバー企業でもあり、本社や工場の見学などもしてきて将来性を確信していたが、実は創業者で会長の齊藤寛さんが先日90歳で亡くなった。現在の山梨県甲州市勝沼町出身の齊藤さんは地元の高校卒業後、20歳だった1954年に甲府市内で焼き菓子店を創業して菓子店の経営を始め、1967年にシャトレーゼを設立して社長に就任した。 洋菓子やアイスクリームなど素材にこだわったものを低価格で販売することで今年1月には店舗が国内外で1000店にまで拡大するなど日本を代表する菓子メーカーに成長させた。
同様の菓子チェーンとして老舗の不二家があるが、銀座から創業した不二家が銀座の価格を全国展開したのに対し、シャトレーゼは地方都市の価格を全国展開しているあたりに経営発想の違いがあると考える。
ドン・キホーテの躍進
2024年8月19日
草創期からマークはしていたが、まさかここまで来るとは正直驚いている。ある意味ユニクロ以上の急成長と言える。「ドン・キホーテ」のホールディング会社、PPIH(パンパシフィックホールディングス)は今や年商2兆円を超える日本有数の小売り業になった。日本はもとよりアジア6か国・地域に45店舗を持ち、ホテルや不動産業などを多角的に経営する企業体にのしあがった。創業者安田隆夫氏が自ら起業、西荻窪駅近くの泥棒市場という名のディスカウントストア(まあ実態は闇市だった)から身を起こし、長崎屋やアピタ(ユニー)といったスーパーを傘下に収め、気が付けば海外にまで展開するビッグビジネスになっていた。
「ドン・キホーテ」の品ぞろえはここにきて食品、なかでも生鮮品の取り扱いが増えている。これはスーパーを買収したことによるメリットだ。とくにシンガポールの店では食品の売り上げ割合が9割を占める。日本の菓子や調味料なども積極的に扱い、日本に行ったことがある人の継続購買を促しているし、「いつか日本に行ったらドンキに寄ってほしい」というメッセージにもなっている。実際シンガポールでの「ドン・キホーテ」の人気は絶大だ。進出から5年足らずで12店舗まで拡大、在留日本人のみならず現地のシンガポール人の間でも歓迎され、刺し身や寿司、そして日本の果物などがよく売れているという。海外の「ドン・キホーテ」の特徴は現地化を徹底していることだ。従業員のほとんどは地元の人で店長以下仕入れから陳列、価格設定までローカル性を重視する。創業者の安田隆夫氏が2015年にシンガポールに移住した際に、現地の日本食品の高さに驚いたことから、この方針を徹底したという。2030年までに海外の売り上げを1兆円まで増やす目標を掲げている。
「ドン・キホーテ」の販売商品は食品以外にも家電から衣類、ドラッグ用品など様々なジャンルに及ぶ、独特の目立ち、長いフレーズのPOPで客の興味をそそる販売手法はあらゆる商品を雑貨的に扱うところに特徴がある。整然としていないことこそオリジナリティある販売手法である、ということだ。百貨店やスーパーと言ったこれまでのビジネスモデルとは対極にある「混沌の泉から湧き出てくるような商品構成」を魅力に変えたことが成功の秘密だろう。
日本人だけでなく外国人からの支持を受けて、日本最大の小売業グループになることも夢ではなくなってきた。
近江屋、伊勢屋、三河屋・・・・
2024年8月19日
世界最古の民間企業は西暦578年創業の大阪の会社、金剛組と言われている。
実に創業1500年近い、寺社建築の実績を誇るこの会社は奈良時代よりも前の飛鳥時代の創業だ。
和菓子の「とらや」は室町時代後期の京都で創業、後陽成天皇の御在位中(1586〜1611)から御所の御用を勤めてきた。明治2年(1869)東京遷都にともない、天皇にお供して京都の店はそのままに東京に移り現在に至る。
日本の企業の歴史は他国を圧倒しており、100年以上の社歴を持つ会社が数多ある。それほど大きな企業でなくても江戸時代以来の伝統を持つ事例は多い。
東京に多い三河屋、駿河屋という屋号の店は徳川とともに今の静岡県や愛知県にルーツを持つ店が江戸に移転し代々引き継がれた由来だろう。
あるいは近江屋は近江商人、伊勢屋は伊勢商人を系譜にしている可能性が大きい。
近江の地は東海道と北國街道が交差し情報と物流の集積地だった。丸紅や伊藤忠、野村證券に高島屋、ふとんの西川などはこの地を起源とする。伊勢もお伊勢参りの参道で人の行き交う地だ。江戸で開花した三井高利から始まる三井グループ、国分などで知られる。ちなみにイオンの起源である岡田屋呉服店はもとをたどれば近江商人だが、その後伊勢街道沿いの四日市に移っている。
地域に根差し、情報のアンテナを張り、そして日本国内はもとより世界へ飛躍していった伝統企業、この日本の企業風土が今後どう変わってゆくか興味深い。
「GS世代研究会」会員企業白洋舎からの提案です
2024年5月 7日
事業統括本部で部長をしております武田順です。皆様には大変お世話になっております。
さて当社では食品等の工場やサービス業で着用されるユニフォーム事業を全国で展開しています。自宅に持ち帰り洗濯などをした場合、衛生基準が満たされないケースもあります。
そこで当社では必要枚数のユニフォームを当社が負担・購入し皆様にレンタルする方式を採用しています。これによりHACCPに対応する安全・衛生なユニフォームをご提供させていただけます。
クリーニング工場もISO22000を取得するなど自信を持っております。
また費用も、同業他社様と比べても大きな差はないはずで、是非一度お見積りを取らせていただければ幸いです。協力工場がありほぼ全国でご要望に応じられます。
詳しくは貼付チラシをご覧の上ご連絡賜りたくお願い申し上げます。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
株式会社白洋舍
事 業 統 括 本 部 武 田 順
〒146-0092 東京都大田区下丸子2-11-8
TEL:03-5732-5101 FAX:03-5732-5153
e-mail: j-takeda@hakuyosha.co.jp