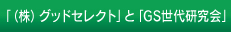投稿西村晃 ★終身雇用制の崩壊
2021年9月13日
投稿 西村晃 ★日本市場攻略の決め手
2021年9月 6日
★ 投稿西村晃 ★これからの日本
2021年8月23日
★一般会員企業「サンプリント」では、自分史、周年記念誌を制作します
2021年8月 1日
★投稿西村晃 国勢調査が示すもの
・2021年8月 (2)
・2021年7月 (7)
・2021年6月 (14)
・2020年11月 (1)
・2020年9月 (1)
・2020年3月 (1)
・2020年2月 (1)
・2019年11月 (1)
・2019年10月 (2)
・2019年7月 (2)
・2019年5月 (1)
・2019年2月 (1)
・2018年10月 (2)
・2018年9月 (2)
・2018年6月 (1)
・2018年5月 (3)
・2018年4月 (3)
・2018年3月 (1)
・2018年2月 (2)
・2018年1月 (1)
・2017年11月 (3)
・2017年10月 (11)
・2015年9月 (1)
投稿 西村晃 ★日本市場攻略の決め手
2021年9月13日
世界的流通業と言えばアメリカのウォルマート、イギリスのテスコ、フランスのカルフール、ドイツのメトロなどがすぐに思い起こされる。
いずれも日本への進出を企て、小売業界では当初「黒船襲来」と大きな話題になった。しかしカルフールとテスコが早々に撤退、このほどメトロも撤退を決めた。残るウォルマートも西友と組んだもののはかばかしい成果を上げているとはいいがたく、2020年には西友の株式の大半を、国際的な投資会社KKR(コールバーグ・クラビス・ロバーツ)と楽天に売却した。ウォルマートは現在も楽天との提携は続けており、かろうじてネットスーパーを共同で運営している。
ほかにもドラッグストア大手セフォラやブーツなど鳴り物入りで日本にやってきたが、いつの間にか消えてしまった外資系小売り企業も多い。
一方でマクドナルドやスターバックス、コストコ、また近年ではアマゾンのように成功しているビジネスもある。さらにIKEAのように一度撤退したものの再進出して成果を上げているところもある。
成功と失敗の間にはどんな違いがあるのだろうか。
私はその答えは自国での成功体験をそのまま持ち込まず、日本市場独自の商慣行や消費者ニーズを取りこむ必要が他国への進出以上に重要なのだと考える。
フランスのカルフールが日本に来た時、問屋を抜いたメーカーとの直接取引を要求した。それを潔しとしなかった日本最大手のビールメーカーやトイレタリー用品メーカーなどの商品が開店時店頭にはなかった。また本国で人気のデリカテッセンを私は購入してホテルで次々に試食したが、どれも脂っこく,量も多すぎると思った。日本人が好む煮物や漬物などは全くなかった。
またテスコもカルフールも自国ではPB商品比率が圧倒的に高く、日本の店でも同じような品ぞろえをしたが、日本人は世界でも有数のナショナルブランドメーカーを好む国民性であった。
同じくセフォラやブーツでもPB化粧品などを店頭に並べたかったようだが、日本では化粧品などの規制が厳しく成分や価格に制約がかかり、品ぞろえに独自性を発揮しにくかったようだ。
IKEAが二度目に日本に来て人気を集めた頃、当時の日本法人社長が、「今回の進出では日本の住宅の寸法にあった商品を用意したし、組み立てや自分で配送できない人のために付加サービスを用意した」と流通新聞のインタビューで語っていた。言い換えれば、そんなことさえ研究せずに日本に来ていたのかと呆れたものだ。
私にとっても意外だったのがコストコの日本での成功だ。
本国のコストコはまとめて大量に販売することで格安価格を可能にしていた。
果たして少人数家庭が多く冷蔵庫のスペースも限られている日本で受け入れられるかと私は懐疑的に見ていた。
日本のコストコでは本国ではあまり見かけない試食販売を多用、日本メーカーの調味料・漬物・ハムなども大箱で扱い、外食産業経営者などの仕入れニーズにも応えた。そしてコストコが最も強みを発揮する大きな塊肉や大量のクロワッサンなどはグループで来店する主婦が、駐車場で購入品をシェアするというパターンを作り出した。ホームパーティー用のローストチキンやピザ、また大皿の握り寿司などが若い家庭に受け入れられ、日本人の購買行動を変えたと言える。
カークランドと呼ばれるPB商品を主力扱いせず、日本市場をにらんだきめ細かいマーケティング戦略が成功したのではないだろうか。
日本市場の特殊性を受け入れ、それに合った戦略をとれるかが、成功のカギであったと分析している。